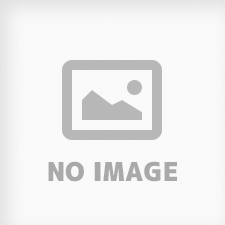昼の長さが一番長い日
夏至は一年で一番昼の長い日といわれます。
子供の頃からずっと『昼が長いってどういうこと?』って思っていました。ここでいう『昼』は太陽が出ている時間のことですね。日の出から日の入りまでの時間です。
最強の紫外線
上のイラストのN、E、W、Sは、北、東、西、南を表しています。
水色の線の重なる十字の部分が自分のいる位置だと考えてください。
冬よりも夏(夏至)に近い程太陽は垂直に近く地面を照らします。
太陽光は大気圏を通る中で実は多少散乱や吸収により弱くなっています。
夏至は地面に届くまでに通過する大気圏の距離が最も短くなるため、可視光(目で感じ取れる光)も紫外線も最強になるのです。
※図中の太陽は角度を表しており、太陽との距離を表しているわけではありません。
紫外線について
地表に降り注ぐ紫外線は、その性質によってUVBとUVAに分けられます。紫外線はお肌にとって『有害』ということはもう一般的に知られていると思います。
しかし実際には良い点として紫外線を浴びることで体内でのビタミンD生成を促す作用があります。
■UVB
主に表皮にダメージを与え、炎症を引き起こし皮膚を赤くしてしまいます。これをサンバーンと呼びます。黒くなる日焼け(サンタン)も引き起こします。
強いエネルギーをもっていますがその分様々なものに遮られやすく、窓ガラスで遮られたり、曇りの日は雲によって晴れの日の量に比べ半減します。
日焼け止めを選ぶ際には『SPF』という表示を参考にしてください。この数字が大きい程UVBを防ぐ力が強くなります。最高値は『50+』です。お出かけ等、日の光を浴びるときはSPF値が大きいものを選んで使うと安心ですね。
■UVA
表皮を通過して表皮の下にある真皮にまで到達し、ダメージを与えます。このことによりメラニン色素が多く作られるため、黒くなる日焼けを起こします。これをサンタンといいます。さらに真皮にあるコラーゲンやエラスチンというタンパク質を壊してしまうのでシワやタルミの原因にもなるので注意が必要です。
UVBよりもエネルギーは弱いのですが、窓ガラスを通過し、曇りの日でも6,7割のUVAが地表に降り注ぎます。
黒くなる日焼けは紫外線を浴びてから24~72時間後に顕著になり、真皮の変化も気づきにくいものなので注意が必要です。※UVBで起こる赤い炎症は2~6時間後に発症するといわれています。
日焼け止めを選ぶ際は『PA』という表示を参考にしてください。『PA+』から『PA++++』の4段階の種類があり、『+』が多い程UVAを防ぐ力が強くなります。
曇りの日でも、室内でもUVAを浴びる可能性は高いので、一日中屋内にいる場合でも特に室内が外の光で明るい場合はUVAを防ぐために日焼け止めを塗ったほうが良いでしょう。
いつの間にか日焼してた、シワやタルミが増えた、とらないために…
■ビタミンD
ビタミンDは紫外線を皮膚に浴びることで皮下脂肪のコレステロールから合成されます。ビタミンDは、食物からのカルシウムの吸収を促進し、骨の成長を助けるため必要なビタミンです。低緯度地域では冬至前後に極夜と言って一日中夜の時期がありますが、フィンランドではこの時期ビタミンDのサプリメントを摂ったり、紫外線を浴びるためのランプがあるそうです。
ビタミンDの生成を促すのはUVBだそうです。そのため窓ガラス越しではなく日光を浴びたほうが良いようです。とはいえ紫外線の強い時期・時間は避けたほうが良いでしょう。日の出や日の入り付近であれば紫外線も弱くなっていますし、木陰などでも紫外線は(反射などによって)浴びることができます。
乳幼児・小児に関して紫外線の害を避けることが広く推奨されるようになり、ビタミンD不足によるくる病(骨の軟化、背が伸びない、下肢が曲がる(O脚やX脚))も増えているようです。
過度はよくありませんが、一度日光浴を見直してもいいかもしれませんね。それとあわせてビタミンDが多い食品を意識的に摂るものよいかと。