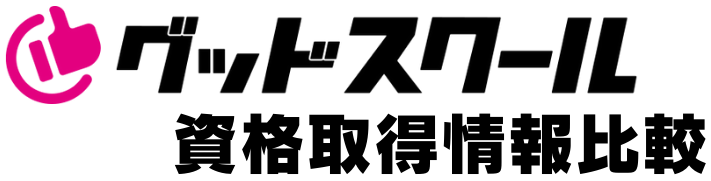公務員試験はどのくらいの難易度なのか気になっていると思いますが、一口に公務員といっても職種によって難易度は全く異なります。
さらに公務員試験は、合格点を取れば受かる資格試験ではなく、採用試験なので競争率も関係します。
どのくらいの人が挑戦し、どのくらいの人が合格したかを知ることである程度の難易度を測ることができるので、この記事では公務員試験の合格率や競争率、さらには人気がある市役所の公務員試験についても調査しました。
公務員試験の全体像を把握し、自身が目指したい分野・職種を明確にし、この難易度を考慮したうえで公務員試験に挑めるように参考にしてみてください。
公務員試験は、通信講座で勉強する方法もおすすめです。
詳しくは、こちらの記事でも解説しています。
公務員とは?
まずは公務員の種類から説明します。
| 国家公務員 |
| ・中央官庁や出先機関で働く ・国家公務員試験(総合職・専門職・一般職)に合格するとなれる ・転勤を伴うが、やりたい分野の仕事に携われる可能性が高い ・総合職と一般職に大別される |
| 地方公務員 |
| ・県庁や市役所などで働く ・地方公務員試験(上級・中級・初級)に合格するとなれる ・転勤の範囲は限られるが、部署間の異動は頻繁に実施される ・一般職・技術職・公安職などに分類される |
公務員とは、大きく国家公務員と地方公務員に分けられます。
名称のように、採用される行政機関が国なのか地方自治体なのかで仕事のスケールが変わり、転勤する範囲の違いや、やりたい分野の仕事に携われるかどうかも違ってきます。
国家公務員の職種には、国会職員・裁判所職員・外務専門職・国税専門官・財務専門官・労働基準監督官・皇宮護衛官・航空管制官・食品衛生監視員などがあります。
地方公務員の職種には、県庁・市役所・区役所に勤務する職員、公立学校の事務職員、警察官、消防官などがあります。
目指したい職種によって、公務員試験の受験区分が変わってきます。
公務員の難易度ランク
こちらでは公務員の職種別難易度をご紹介します。
公務員試験の中には教養試験だけではなく、専門試験を実施する分野もあります。
専門試験がある公務員試験の方が専門知識を要するので難易度が高い傾向です。
大手通信教育講座のサイトや口コミを参考に、難しい方から難易度S・難易度A・難易度B・難易度Cの順にランク分けしましたので、自身が興味のある職種がどのくらいの難易度に位置づけされているかを目安にしてください。
難易度S
| 難易度S |
| ・国家公務員(総合職) ・外務省専門職 ・国会職員 |
試験問題のレベル・競争率ともに高く、面接試験でも適性や人柄などを厳しくチェックされます。
国家公務員(総合職)は財務省・総務省・経産省などのいわゆるキャリア官僚の採用試験です。
高難度の筆記試験や面接試験に加え、各中央省庁の採用面接(官庁訪問)もあり、エリートたちが挑戦する有数の難関試験です。
外務省専門職は国際的に活躍するための抜群な語学力と専門知識が求められます。
採用数も少なく、競争率が高い試験です。
国会職員は、衆参議員職員や国立国会図書館職員としてハイレベルな専門性を求められます。
難易度の高い筆記試験の上、採用枠も限られるため競争率も高いのが特徴です。
難易度A
| 難易度A |
| ・労働基準監督官 ・航空管制官 ・東京都庁I類・都庁圏県庁(上級)・政令指定都市職員(上級)・東京23区職員 |
労働基準監督官や航空管制官は、専門性が高く試験レベルも高度です。
採用枠も限られているので、難易度も競争率も高い難関試験といわれています。
東京都都庁I類・都庁圏県庁(上級)・政令指定都市職員(上級)は大卒者の中でも特に成績優秀者が目指す試験として知られており、東京23区職員も人気があり難関試験にあたります。
大都市圏や政令市は予算規模が大きいので、地方公務員でありながらも大きな規模感で仕事ができるのが魅力になっており、年収も高く都市部に位置するため非常に人気があります。
難易度B
| 難易度B |
| ・国家公務員(一般職) ・地方公務員(上級) ・国税専門官 |
国家公務員(一般職)や地方公務員(上級)は公務員志向の強い地方では、地元大学生を中心に人気が高い傾向にあります。
どちらも一般的な事務を担うので、公務員試験で最大のボリュームゾーンであり、試験の内容も典型的です。
国税専門官は国家公務員(一般職)よりも年収が高く、人気があります。
専門的な試験がありますが、採用枠が多いのが特徴です。
また、勤続年数によって税理士試験が免除される特典があるので、定年後も税理士としてのセカンドキャリアが期待できます。
難易度C
| 難易度C |
| ・市役所 ・消防官 ・警察官 |
難易度Cになると、短期間の学習や独学での勉強で合格できるケースも少なくありません。
ただし、競争率が高い人気の職種はしっかり準備して挑む必要があります。
多くの市役所の筆記試験は教養試験・論文試験のみになっており、他の公務員試験に比べると学習の範囲が狭いのが特徴です。
教養試験の代わりにSPI3というリクルートが開発した適性検査を導入している市役所もあり、民間企業との併願受験をするケースも多くみられます。
消防官や警察官も筆記試験は教養試験・論文試験のみです。
体力試験もあるので、勉強だけでなくトレーニングなどをして備える必要があります。
国家公務員の難易度を合格率と倍率から解説
| 国家公務員採用試験の種類 |
| ・国家公務員採用試験(院卒者・大学卒業程度) ・国家公務員採用試験(高校卒業程度) |
上記の2025年度(令和7年度)合格率や倍率を一覧表にまとめました。
国家公務員採用試験の院卒者とは大学院の過程を終了した人のことです。
大学卒業程度とは、大学卒業程度の問題による試験ということで受験資格を満たしていれば学歴関係なく受験できますが、各試験によって受験資格が違うので注意が必要です。
公務員試験の合格基準ラインは?
合格率を紹介する前に、合格基準ラインを説明します。
資格試験とは違い、公務員試験のように採用枠が決まっている採用試験では、合格者数を基準にボーダーラインを設定する相対評価が用いられます。
目安とされているボーダーラインは、教養科目が約6割、専門科目が約7割と言われている事が多いようです。
しかし、その年の受験者数やレベルによって変動する上、2次試験で行われる面接もクリアする必要があります。
公務員試験においては合格基準ラインという概念が通用しにくい試験とも言えるでしょう。
国家公務員採用試験(院卒者・大学卒業程度)の合格率と倍率
国家公務員採用試験(院卒者・大学卒業程度)の2025年度(令和7年度)合格率・倍率は以下の通りです。
| 種類 | 試験名 | 申込者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 合格率
(最終合格者数/申込者数) |
| 国家公務員試験 | 総合職試験(院卒者試験) | 1,288人 | 928人 | 640人 | 49.7% |
| 総合職試験(大卒程度) | 10,740人 | 2,200人 | 1,153人 | 10.7% | |
| 一般職試験(大卒程度) | 25,437人 | 12,152人 | 8,815人 | 34.7% | |
| 国税専門官採用試験(大卒程度) | 10,512人 | 6,039人 | 3,394人 | 32.3% | |
| 一般職試験(高卒程度) | 8,275人 | 4,594人 | 3,338人 | 40.3% |
(人事院HPを参考に申込者数と合格者から算出)
こちらの表の中では、総合職試験(院卒者・法務区分)が49.7%と高い合格率です。
院卒者・法務区分は、大学院の過程を終了した人しか受験資格が得られないので競争率も低く、さらに法務という専門知識が必要な区分なので、しっかり試験対策して挑んだ方が多かったと考えられます。
一方で、1番低い合格率が2022年の皇宮護衛官(大卒者程度試験)の2.6%です。
採用予定人数20名程度に対しての受験者数が多いのが影響しているとみられており、2020年は4.7%、2021年は5.6%と皇宮護衛官(大卒者程度試験)の合格率はいずれも低くなっております。
1番受験者数の多い試験が、一般職試験(大卒者程度試験)ですが、合格率は2019年は25.4%、2020年は21.1%、2021年は27.6%と狭き門になっています。
国家公務員採用試験(高校卒業程度)の合格率と倍率
国家公務員採用試験(高校卒業程度)の2025年度(令和7年度)合格率・倍率は以下の通りです。
| 採用試験 | 合格率/倍率・2025年度(令和7年度)
※合格者数/申込者数 |
| 一般職試験 (高卒者試験) |
40.3%
2.5倍 |
| 一般職試験 (社会人試験) |
19.0%
5.3倍 |
| 皇宮護衛官 (高卒者程度試験) |
6.4%
15.6倍 |
| 刑務官 | 29.0%
3.5倍 |
| 入国警備官 | 18.9%
4.9倍 |
| 税務職員 | 37.4%
2.7倍 |
| 航空保安大学校学生 | 28.9%
3.5倍 |
| 気象大学校学生 | 20.9%
4.8倍 |
| 海上保安大学校学生 | 24.1%
4.1倍 |
(人事院HPを参考に申込者数と合格者から算出)
こちらの表で高い合格率は、一般職試験(高卒者試験)で40.3%(3.3倍)です。
一方で、合格率がたったの6.4%が皇宮護衛官採用試験です。
大卒者試験と同じく、こちらでも一般職試験(高卒者試験)が1番受験者が多い試験ですが、2019年19.8%、2020年22.2%、2021年24%と低い合格率なので、しっかりとした試験対策が必要になってくるでしょう。
地方公務員の難易度は?人気の高い市役所の合格率と倍率から解説
ここまでは国家公務員の難易度をみてきましたが、次は地方公務員の難易度を解説していきます。
地方公務員の職種も様々ですが、その中でも市民生活をサポートする身近な公務員として人気が高いのが市役所職員です。
市役所職員になるため試験概要や難易度を解説していきますので、市役所の公務員試験に合格するための参考にしてください。
市役所の試験区分・受験資格
市役所の公務員試験は、事務系と技術系に分けられます。
事務系は行政業務を担当し、技術系は電気・機械・土木・建築などの専門分野を担当します。
一般的には事務系の募集人数が多く、技術系は少ない傾向にあります。
さらに公務員試験は、仕事内容と試験の難易度によって区分が異なり上級・中級・初級があります。
| 上級 |
| ・幹部候補 ・大卒程度のレベル |
| 中級 |
| ・短大卒程度のレベル ・市役所によって設けていない場合もある |
| 初級 |
| ・一般事務職員 ・高卒程度のレベル |
市役所の公務員試験の受験資格は、地方自治体の大部分が日本国籍を持つことを条件にしています。
年齢制限は、30歳前後が一般的ですが市役所によっては25歳までの制限だったり、50歳以上でも受験可能な場合もあります。
学歴も不問で、大卒程度・高卒程度というのはレベルの目安であり大学や高校を卒業していなくても受験できます。
受験時点での居住地も問われませんが、採用後に市役所のある自治体への移住が義務付けられているところもあるので希望する市役所の受験資格をしっかり確認しましょう。
横浜市令和7年度大学卒程度等採用試験の合格率と倍率
市役所は日本全国さまざまなところにありますが、ここでは横浜市の合格率や倍率を解説します。
まずは、令和7年度の大学卒業程度採用試験です。
| 試験区分 | 受験者数 | 最終合格者数 | 最終競争率(倍) |
|---|---|---|---|
| 事務 | 1,216 | 270 | 3.1 |
| 社会福祉 | 311 | 87 | 2.8 |
| 心理 | 100 | 22 | 3.7 |
| 土木 | 48 | 14 | 2.4 |
| 建築 | 27 | 6 | 3.2 |
| 機械 | 14 | 4 | 2.8 |
| 電気 | 11 | 2 | 5.0 |
| 農業 | 11 | 2 | 4.0 |
| 造園 | 26 | 4 | 5.5 |
| 環境 | 26 | 3 | 5.7 |
| 衛生監視員 | 77 | 8 | 6.8 |
| 保健師 | 92 | 11 | 7.5 |
| 消防 | 395 | 66 | 4.4 |
| 消防(救急救命士) | 126 | 32 | 2.7 |
| 学校事務 | 58 | 17 | 2.4 |
| 合計 | 2,538 | 548 | 3.4 |
(引用元:横浜市HP)
こちらの表では受験者数の多い事務の試験は競争率3.1倍と競争の激しさが分かります。
さらに環境の試験も5.7倍と高いことが分かります。
環境は主に工場の規制指導・環境保全のための調査研究・地球温暖化対策など環境施策に係る企画・立案などの業務に従事できますが、採用予定数が数人程度と募集自体が少ないので競争率が高くなる傾向です。
競争率が2.8倍と低いのが、社会福祉の試験です。
社会福祉は主に区役所や児童相談所、社会福祉施設などで指導・相談・調査などの業務に従事できます。
日本の超高齢社会に合わせてなのか採用予定数も多いので競争率も低い傾向です。
横浜市令和7年度高校卒程度・免許資格職など採用試験の合格率と倍率
次に、令和7年度の高校卒程度採用試験です。
| 試験区分 | 受験者数 | 最終合格者数 | 最終競争率(倍) |
|---|---|---|---|
| 事務 | 244 | 11 | 16.5 |
| 土木 | 8 | 1 | 4.0 |
| 機械 | 3 | 1 | 3.0 |
| 電気 | 3 | 1 | 2.0 |
| 水道技術 | 6 | 4 | 1.3 |
| 保育士 | 135 | 39 | 2.4 |
| 司書 | 87 | 6 | 10.8 |
| 栄養士 | 67 | 2 | 23.0 |
| 消防 | 398 | 106 | 2.9 |
| 消防(救急救命士) | 127 | 47 | 2.1 |
| 学校栄養 | 62 | 3 | 16.3 |
| 合計 | 1,140 | 221 | 3.9 |
(引用元:横浜市HP)
こちらの表では受験者数が多い事務の試験は競争率約16.5倍となっており競争が激しくなっております。
さらに10.8倍と高い競争率なのが司書の試験です。
司書は、主に図書館などにおいて司書として資料を収集・分類整理するほか、資料の貸出や読書案内などの専門的業務に従事できますが採用予定数が数人と少ないため競争率が高くなる傾向です。
競争率が低いのが土木・機械・電気の試験ですが、専門的分野の中では採用予定数が10人程度と多めです。
その割には、受験者数が少ないので競争率の低さに影響してます。
主に総合的な都市整備や道路・河川・上下水道・湾港・地下鉄などの計画や建設において、土木関係の専門的技術の業務に従事します。
ここでは、横浜市を例に説明しましたが、希望する自治体や気になっている自治体があれば、その自治体のホームページからご覧になり比較してみることでよりイメージしやすくなるかと思います。
公務員試験が難しい理由は?
公務員試験が難しいといわれている理由を、口コミや大手通信教育講座のサイトから以下の3つにまとめました。
| 公務員試験が難しい理由は? |
| ・試験範囲が広い ・面接試験の難易度が上がっている ・採用人数が決まっている |
それぞれ詳しく解説していきます。
試験範囲が広い
公務員試験は出題科目がとても多く、試験範囲は膨大です。
国家一般職(行政)を例に挙げると、筆記試験は基礎能力を問われる知能・知識分野に加えて、以下の16科目から8科目を選択して解答する必要があります。
| 国家一般職(行政)の選択科目 |
| ・政治学・行政学・憲法・行政法・民法(総則及び物権)・民法(債権、親族及び相続)・ミクロ経済学・マクロ経済学
・財政学・経済事情・経営学・国際関係・社会学・心理学・教育学・英語(基礎)・英語(一般) |
このように勉強する範囲が広い上、理解が難しい問題もあるので合格するレベルまでもっていくには簡単ではないでしょう。
面接試験の難易度が上がっている
公務員試験は筆記試験を合格すると、2次試験へと進めます。
2次試験は主に面接試験や論文試験で構成されていますが、最近の公務員試験は人物重視の傾向が強く出ているといわれています。
筆記試験は勉強すれば結果につながりやすいですが、面接試験や論文試験はやや不透明なところが多いので何をすれば合格に近づけるのかが明確ではありません。
筆記試験に比べると対策が難しいと言えるでしょう。
採用人数が決まっている
公務員試験は採用試験なので、合格点以上を取れば合格というわけではありません。
どの公務員試験も採用予定数より多くの受験者が集まり競争率が高まるので、満点に近いほど有利になります。
日本の人口減少に伴い、採用予定数が減少傾向にありますが自治体や職種によっては採用予定数が増加する場合もあるので興味があるところはしっかりとチェックしましょう。
しかし、合格する=就職するということなので、受かりやすさだけを求めずに自分が働きたいところを重視するのも大事です。
志望先の選び方
公務員試験は、主に教養試験・専門試験・論文試験・面接試験があり、職種によっては体力検査や身体検査もあります。
それぞれの試験で問われる科目や分野は多くの職種で共通する上、公務員試験の日程は自治体によって異なるため、併願受験も可能になります。
国家公務員試験や地方公務員試験、民間企業との併願受験をする人も少なくありません。
公務員試験に受験回数の制限はなく、受験料も原則無料ですが、日程を考えると5~7カ所が上限になるでしょう。
しかし、併願受験で合格する確率を上げるのも一理ですが、あくまで採用試験になり合格した後に働くことを考えると、どの職種についてどんな仕事がしたいかという事が1番大切なのではないでしょうか。
最近の公務員試験は人物重視の傾向が強く出ているといわれているので、希望の職種を優先して志望先を選択することが面接でのアピールポイントを強くする要因になるでしょう。
公務員試験に合格するための勉強方法
| 会社名 | 学習目安時間 |
| LEC | 800~1500時間 |
| ユーキャン | 最低800時間 |
| アガルートアカデミー | 1500〜1600時間 |
公務員試験で合格するために必要な勉強時間を調査したところ、800~1600時間という事が大手通信教育講座のサイトから分かりました。
受験したい職種や出身学部、得意科目の有無によって勉強時間は変わりますが、試験の1年前から勉強を開始する受験生が大多数です。
公務員試験の試験範囲はとても広いため、膨大な量の学習が必要になります。
その膨大な量の学習を大学の授業や卒論制作、さらには民間企業との併願を考えている方は就職活動と並行して行わなければなりません。
そのためには、計画的に勉強時間を捻出できるようになるべく早い時期からスケジュールを決める必要があります。
公務員試験を独学で勉強するのなら、なおさら早めの学習はかかせません。
計画的・効率的に勉強する自信がない方は、予備校や通信講座の受講を考えるのも合格への近道になるかもしれません。
市役所の公務員試験の勉強スケジュール
ここでは、市役所の公務員試験を例に、試験開始までのおおまかなスケジュールについて解説します。
参考にしたサイトは、国家公務員として省庁で働いた後、現在は公務員試験の面接指導や論文添削をおこなっている、わんこ先生が運営する「はじめて公務員」や、実際に公務員試験に合格した人のサイト「公務員試験の内容と勉強方法」です。
9~12月の公務員試験勉強スケジュール
教養試験は、一般知能の勉強からスタート。
一般知能の分野は出題数がとても多いので、早めにコツコツ勉強することで得点力が身に付きます。
専門試験は、択一式から始めることで教養試験の一般知能の部分を一部カバーしているので効率よく進めやすいです。
1~3月の公務員試験勉強スケジュール
教養試験の一般知識の勉強も始め、論文対策や時事問題対策も行います。
一般知識は、人文科学・自然科学・社会科学・時事と非常に多くの科目で構成されていますが、その多くの科目に関係する時事問題の学習に集中するのが得策といえるでしょう。
論文対策は過去の合格者が考えた論文をアレンジして自分の考えを入れる方法が効率よく対策できます。
4~6月の公務員試験勉強スケジュール
教養試験・専門試験の総復習をして、よく理解できていないところを洗い出し特訓しましょう。
勉強の合間に、面接試験対策も始めます。
面接試験の配点比重を高くしている自治体が増えているので、早いうちから少しずつ対策しておくのも重要です。
いよいよ公務員試験スタート
1次試験が終われば2次試験に集中できるので、最後まで気を抜かず面接対策を仕上げましょう。
集団面接や集団討論など様々な面接試験が実施されていますので、希望する自治体がどういう面接試験なのかしっかり調べて対策することが必要です。
ここまで大まかなスケジュールをお伝えしましたが、独学・予備校・通信講座などの勉強方法によっても変わってきますので、参考程度に自分の勉強スタイルに合わせてアレンジしてください。
公務員試験の勉強には予備校や通信講座がおすすめ
公務員試験は独学でも効率よく勉強を進めることで合格は十分可能です。
しかし、採用試験なので合格のボーダーラインが予想しにくい上、膨大な量の試験範囲や面接対策などを考えると公務員試験予備校や通信講座を受講することをおすすめします。
イメージしやすいように、独学・通信講座・予備校で勉強する場合のメリットとデメリットをまとめました。
| 勉強方法 | メリット | デメリット |
| 独学 | ・費用が安い ・自分のペースで勉強できる |
・不明点があってもすぐ質問できない ・モチベーションの維持が難しい |
| 通信講座 | ・予備校よりは費用が安い ・効率よく勉強できる |
・リアルタイムで質問できない ・解約しても返金制度がないことが多い |
| 予備校 | ・プロの講師に教えてもらえる ・不明点をすぐ質問できる ・モチベーションが保ちやすい |
・費用が高い ・通学時間が必要 |
独学のメリットは何といっても費用が安いことです。
サポートがないので、計画的に勉強することが得意な方や、不明点があっても自分でコツコツ勉強を続けて理解する力がある人が独学に向いてるとされています。
通信講座のメリットは、合格のノウハウが詰まったテキストやWEB映像などが用意され、それらを効率よく勉強できるところです。
各通信講座によって異なりますが、比較的費用が安く、質問やカウンセリングを受け付けてくれるところもあります。
独学に比べるとモチベーションを維持しやすい傾向ですが、途中でやる気がなくなり解約したくても返金制度がないことが多いのでしっかりとした学習計画を立てて実行することが必要になります。
予備校のメリットは、合格へのノウハウが蓄積されている学校で試験合格への手厚いサービスを受けれることです。
計画的に学習を進められる通学スタイルで、プロの講師やスタッフも多く、受講生1人1人にきめ細やかなサポートを行う特徴があります。
その分、費用が高く、通学時間の確保なども必要です。
公務員試験の予備校や通信講座のさらに詳しい情報を知りたい方は下のリンクからご覧ください。
おすすめの公務員試験対策予備校・通信講座
ここでは公務員試験対策におすすめの予備校や通信講座をご紹介します。
おすすめの公務員試験予備校
公務員試験予備校の中でも、特におすすめなのが資格の大原です。
ほとんどの人が名前を聞いたことがあるくらい、予備校の中でも最大手です。
特徴は、さまざまな公務員試験に対して多彩なコースが設定されており、公務員を目指す受講者に合わせた対策が立てやすいところです。
プロの講師陣による講義や充実したサポート、オリジナル教材など合格に向けたノウハウが豊富です。
長年に渡り公務員試験予備校としての実績を積み重ねており、受講生からの評判も非常に良いので、合格に直結しやすい予備校だと言えます。
安心の合格実績もあり、2024年度公務員行政事務系採用試験は3,156名合格者を輩出しています。
おすすめの通信講座

近くに通える予備校がなかったり費用面で通えない人は、通信講座の利用も検討の余地があります。
通信講座では、スタディングがおすすめです。
スタディングの教材は、WEBテキストなので手軽に利用しやすく、通学や通勤の隙間時間も活用できるので学習効率が上がるでしょう。
また、他の通信講座に比べてとてもリーズナブルな上、エントリーシートの添削や面接指導も行っています。
得点に結びつくところを重点的に押さえ、それ以外のところは重要な部分を押さえつつコンパクトに学べるカリキュラムになっています。
公務員試験の難易度に関するよくあるQ&A
| 公務員試験の難易度に関するよくある質問 |
| ・市役所の公務員試験の難易度はどのくらい? ・公務員試験は難しすぎるって本当?難しい理由は? ・公務員試験の高卒程度の難易度は? ・公務員の志望先はどうやって決める?簡単になれる職種はあるの? ・公務員試験は無理ゲー?受かる気がしないんだけど… ・公務員の就職に強い大学は関西地方ではどこがあるの? |
公務員試験の難易度に関するよくある質問にお答えしていきましょう。
市役所の公務員試験の難易度はどのくらい?
A.市役所の試験区分によって難易度は変わりますが、一例として令和7年度の横浜市の公務員試験(大学卒業程度採用試験)はこのようになっております。
| 試験区分 | 受験者数 | 最終合格者数 | 最終競争率(倍) |
|---|---|---|---|
| 事務 | 1,216 | 270 | 3.1 |
| 社会福祉 | 311 | 87 | 2.8 |
| 心理 | 100 | 22 | 3.7 |
| 土木 | 48 | 14 | 2.4 |
| 建築 | 27 | 6 | 3.2 |
| 機械 | 14 | 4 | 2.8 |
| 電気 | 11 | 2 | 5.0 |
| 農業 | 11 | 2 | 4.0 |
| 造園 | 26 | 4 | 5.5 |
| 環境 | 26 | 3 | 5.7 |
| 衛生監視員 | 77 | 8 | 6.8 |
| 保健師 | 92 | 11 | 7.5 |
| 消防 | 395 | 66 | 4.4 |
| 消防(救急救命士) | 126 | 32 | 2.7 |
| 学校事務 | 58 | 17 | 2.4 |
| 合計 | 2,538 | 548 | 3.4 |
(引用元:横浜市HP)
上の表の合格率(倍率)の平均は3.4倍(約21.6%)です。
公務員試験は難しすぎるって本当?難しい理由は?
A.公務員試験が難しいと言われている理由を口コミや大手通信教育講座のサイトから調査すると、以下の3つが挙げられました。
| ・試験範囲が広い ・面接試験の難易度が上がっている ・採用人数が決まっている ・公務員試験は無理ゲー?受かる気がしないんだけど… ・ |
公務員試験の試験範囲は膨大な上、人物重視の傾向が強く出ているので面接試験の難易度が上がっています。
採用人数が決まっているのが他の資格試験に比べると難しいと言われる理由に挙げられます。
公務員試験の高卒程度の難易度は?
A.公務員試験でも国家公務員か地方公務員かによっても難易度は変わってきますが、一例として国家公務員採用試験(高校卒業程度)の2025年の合格率・競争率はこちらです。
| 採用試験 | 合格率/倍率・2025年度(令和7年度)
※合格者数/申込者数 |
| 一般職試験 (高卒者試験) |
40.3%
2.5倍 |
| 一般職試験 (社会人試験) |
19.0%
5.3倍 |
| 皇宮護衛官 (高卒者程度試験) |
6.4%
15.6倍 |
| 刑務官 | 29.0%
3.5倍 |
| 入国警備官 | 18.9%
4.9倍 |
| 税務職員 | 37.4%
2.7倍 |
| 航空保安大学校学生 | 28.9%
3.5倍 |
| 気象大学校学生 | 20.9%
4.8倍 |
| 海上保安大学校学生 | 24.1%
4.1倍 |
(人事院HPを参考に申込者数と合格者から算出)
公務員の志望先はどうやって決める?簡単になれる職種はあるの?
公務員試験は、あくまで採用試験になり合格した後に働くことを考えると、どの職種についてどんな仕事がしたいかという事がとても大切になるかと思います。
簡単になれる職種だけで決めてしまうと、面接試験で不利になってしまう場合もあります。
最近の公務員試験は人物重視の傾向が強く出ているといわれているので、希望の職種を優先して志望先を選択すれば面接でのアピールもしっかりできることでしょう。
公務員試験は無理ゲー?受かる気がしないんだけど…
公務員試験は競争率が高い傾向ですが無理ゲーではありません。
受験料が原則無料なので、併願受験をする人が多いことが競争率を上げている側面もあります。
対策をしっかり考えて効率よく勉強すれば合格も可能ですが、計画的に勉強することが苦手な方は予備校や通信講座を利用するのをおすすめします。
公務員の就職に強い大学は関西地方ではどこがあるの?
A.2024年の国家公務員採用総合職試験(院卒者・大卒程度試験)の出身大学別合格者一覧はこちらです。
| 大学名 | 全区分(人) | うち春試験分(人) | うち秋試験分(人) |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 345 | 189 | 156 |
| 京都大 | 179 | 120 | 59 |
| 早稲田大 | 119 | 72 | 47 |
| 東北大 | 90 | 73 | 17 |
| 慶應義塾大 | 88 | 51 | 37 |
| 立命館大 | 86 | 84 | 2 |
| 大阪大 | 72 | 58 | 14 |
| 北海道大 | 70 | 58 | 12 |
| 千葉大 | 68 | 63 | 5 |
(引用元:人事院提供データ)
上位10大学をあげましたがこの中で関西地方の大学は京都大学・立命館大学・大阪大学となります。
公務員試験 難易度のまとめ
公務員試験の難易度・合格率などを見てきましたが、難関試験から比較的受験しやすい試験まで様々です。
さらに、その年の受験者数で競争率は変わるので国家公務員試験の方が地方公務員試験より難易度が高いと一概に決めることも難しいです。
採用予定数も受験する年や各自治体によって変わるので、運によるところもあるのが大きいでしょう。
しかし、自分が興味がある公務員試験がどの程度のレベル・合格率・競争率かを知ることで少しは効率の良い学習計画に役立つことと思います。
確実に合格を勝ち取るために、自分がなりたい職種を見極めて早めに学習計画をたて効率よく勉強をスタートしましょう。
公務員試験の勉強をスタートするにあたりもっと詳し情報が知りたい方は、こちらのリンクからご覧ください。