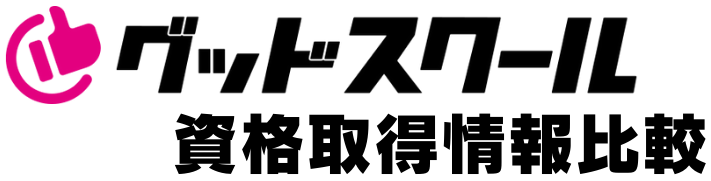登録販売者とは、ドラッグストアやコンビニエンスストアなどに常駐し、風邪薬や鎮痛剤などの一般用医薬品を販売できる専門資格です。
高齢化社会や生活習慣病の増加を背景に、薬剤師がいなくても医薬品を販売できる登録販売者のニーズはさらに高まっていくと考えられています。
しかし、「登録販売者ってどんな仕事をしているんだろう?」「他の店員さんと同じような仕事をしているけれど、登録販売者の資格を持っていて意味があるのかな・・・」など、疑問に思った方もいるかもしれません。
この記事では、
・登録販売者はどんな仕事をしているの?
・登録販売者の資格ってぶっちゃけ役に立つの?
という方に、登録販売者の資格を取得するメリットとデメリット、登録販売者資格の将来性などをご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
登録販売者試験は、通信講座や予備校を利用した学習方法もおすすめです。
登録販売者のおすすめ通信講座の記事でも詳しく解説しています。
登録販売者とはどのような資格なの?
登録販売者とは、一般用医薬品の販売に必要な専門資格です。
2009年の改正薬事法の施行により誕生しました。
風邪薬・鎮痛剤など、一般用医薬品のうち第2類医薬品と第3類医薬品を販売できます。

引用元:ユーキャン公式HP
※「一般用医薬品」とは・・・いわゆる市販薬で、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる医薬品のことです。登録販売者が扱える第2類・第3類医薬品は一般用医薬品のうち9割以上を占めています。
つまり、登録販売者がいれば一般用医薬品のうちほとんどすべての品目を取り扱えるため、薬剤師不在でも一般用医薬品を販売できる専門家として注目されているのです。
登録販売者の主な仕事は
医薬品の販売、薬選びのサポートや薬の内容に関する情報の提供、健康相談が主な仕事です。
医薬品を販売するだけではなく、医薬品を求めて来店したお客様の視点に立ち、適切な医薬品を選べるようにサポートすることが求められます。
また、ドラッグストアで勤務する場合は、商品の仕分けや品出し、発注からレジ打ちまで、ドラッグストアの仕事全般も行います。
登録販売者に向いている人は?
登録販売者として働くのに向いている人は、
・責任感がある人
・医薬品に興味がある人
・人と接することが好きな人
です。
まず、医薬品を購入したい方に適切な医薬品の紹介やアドバイスをすることは、とても大きな責任が伴う仕事です。
真剣に仕事に向き合い、医薬品のプロフェッショナルとしての責任感を持ち、適切に判断できる人が登録販売者に向いているといえます。
医薬品に興味があり、ずっと関心を持ち続けられることも重要なポイントです。
医薬品は次々と新しいものが発売されるため、医薬品にまつわる最新情報を常に集めて発信していく必要があります。
また、登録販売者の仕事は医薬品を求めるお客様の話を聞くことから始まります。
人と接することが好きで、お客様への思いやりを持ち、悩みや相談に耳を傾けられる人も、登録販売者に向いているといえるでしょう。
増えすぎ?登録販売者試験の合格者は年々増加している
登録販売者試験は、2015年度の試験から受験資格が撤廃され、実務経験や学歴が不問となりました。
誰でも受験できるようになった結果、受験者数の増加に伴い合格者数も増え続けています。
また、登録販売者試験の合格者数の累計は令和6年時点で43万人に上っており、登録販売者が増えすぎることによって雇用が不安定になるなど、将来性に不安を持つ方もいるかもしれません。
しかし、2021年8月に医薬品販売に関する規制緩和が行われた結果、登録販売者の活躍の場は今後さらに増えていくことが予想されています。
登録販売者の主な勤務先であるドラッグストアの店舗数は年々増加し続けており、さらに大手コンビニチェーンのローソンは、2023年をめどに医薬品販売可能な店舗を450店舗に倍増させる目標を示しています。
また、インターネットでの一般用医薬品販売の普及により、ネット販売業者やコールセンターでも登録販売者の求人がみられるようになりました。
よって、登録販売者の数が増え続けていったとしても、今後登録販売者の需要が減る可能性は低いと考えられます。
登録販売者として働くメリット4選

引用元:ユーキャン公式HP
| 登録販売者として働くメリット4選 |
| ・需要が高く、就職・転職がしやすい
・資格手当がつき、給料が上がる ・仕事の幅が広がり、自分自身のキャリアアップにもつながる ・身に着けた知識を様々な場面で活かせる |
では、ここでは登録販売者として働くメリット4つについて解説していきます。
需要が高く、就職・転職がしやすい
登録販売者の主な勤務先はドラッグストアや調剤薬局であり、これらの店舗数は現在も増え続けています。
経済産業省の統計によると、2024年1月では全国のドラッグストア店舗数が26,462店に上っており、さらに厚生労働省の統計によると、調剤薬局は2021年に61,791店を超えました。
また、大手コンビニチェーンでも一般医薬品を取り扱う店舗が増えています。
ローソンでは2023年をめどに医薬品を取り扱う店舗を450店舗まで増やす計画を立てており、ファミリーマートではドラッグストアや調剤薬局と一体型の店舗を開業するなど、登録販売者を必要とする場はさらに増えていくと予想されます。
身に着けた知識やスキルを活かしながら全国どこでも働けるため、就職・転職に有利であるといえます。
資格手当がつき、給料が上がる
登録販売者の資格を持っていると、資格手当が支給され給料がアップします。
正社員であれば、勤め先によりますが月給に10,000円~20,000円程度資格手当が支給されるようです。
またパートの場合は、資格手当として時給が200~300円程度上乗せされることが多いようです。
大手ドラッグストア3社の実際の求人情報を参考に、正社員とパート・アルバイトの登録販売者の資格手当について以下にまとめました。
| 企業 | 正社員の資格手当(月額) | パート・アルバイト(時給) |
| A社 | 15.000円 ※法定研修中は5,000円 |
【資格あり】 1,290円~1,807円 ※法定研修中は時給1230円 |
| 【資格なし】 1,200円~1,250円 |
||
| B社 | 最大10,000円 | 【資格あり】 1,300円 |
| 【資格なし】 1200円 |
||
| C社 | 10,000円 | 【資格あり】 1,150円 ~ 1,300円 |
| 【資格なし】 1100円 ~ 1150円 |
※「法定研修中」・・・実務経験2年未満の場合
※パート・アルバイト時給はいずれも東京都内の求人を参照
同じ仕事をしていても、資格を取得するだけで収入アップが見込めるのは大きなメリットですね。
仕事の幅が広がり、自分自身のキャリアアップにもつながる
登録販売者は医薬品を扱うための専門資格であり、取得することで昇進を目指しやすくなります。
特にドラッグストアなどにおいては、店舗管理者は登録販売者資格を持っていることが必須条件とされています。
また、実務経験などの条件を満たし、開業許可や販売許可を取得できれば、将来的に独立し開業することもできるようになりました。
登録販売者の資格を取得することが、自分自身のキャリアアップの土台を作ることにつながるのです。
身に着けた知識を様々な場面で活かせる
登録販売者の医薬品に関する幅広い知識は、自分や家族、友人等の健康を守るために活かせます。
家族が風邪を引いたときなど、どのような薬を飲めばいいのか、注意しなければならない副作用は何かなどがわかるため、家族の体調不良時に適切な対応ができるようになるでしょう。
また、介護の現場や保育園など、医薬品を扱う業種以外に就職しても、医薬品の知識が役に立つ場面が多くあると考えられます。
登録販売者として働くデメリット3選

引用元:資格のキャリカレ公式HP
| 登録販売者として働くデメリット3選 |
| ・実務経験を積めないと正規の登録販売者と認められない
・立ち仕事が多く、体力が必要 ・商品の販売ノルマが課せられることもある |
次に、登録販売者として働くデメリット3つについて解説していきます。
実務経験を積めないと正規の登録販売者と認められない
登録販売者試験に合格した後、すぐに登録販売者として働けるわけではありません。
正規の登録販売者として働くためには、直近5年の間に通算2年分以上の実務経験が必要となります。
特に未経験で登録販売者試験に合格した場合、2年の実務経験を積むまでは研修中の登録販売者として扱われるため、研修中期間は資格手当なども低くなります。
立ち仕事が多く、体力が必要
登録販売者の主な仕事は医薬品の販売や相談業務ですが、レジ打ち、品出し、発注業務等の仕事を任されることもあり、業務時間中は基本的に立ち仕事が続きます。
また、販売員としての接客スキル、コミュニケーション能力も求められます。
体力が追い付かずに退職してしまう人もいるため、体力に不安を抱えている人はあらかじめ仕事の内容を確認しておくとよいでしょう。
商品の販売ノルマが課せられることもある
登録販売者がドラッグストア等に勤務する場合、企業が推奨する商品の販売ノルマを課せられることがあります。
医薬品や健康食品、化粧品などの推奨品、企業のプライベートブランドなどの利益が出やすい商品をお客様に勧めることで、売り上げ目標達成を目指さなければなりません。
ノルマを意識することでお客様に寄り添った接客ができなくなり、販売ノルマがあること自体をストレスに感じる人も多いようです。
登録販売者として働くメリットとデメリットまとめ
登録販売者として働くメリットとデメリットについて、以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・需要が高く、就職・転職がしやすい ・資格手当がつき、給料が上がる ・仕事の幅が広がり、自分自身のキャリアアップにもつながる ・身に着けた知識を様々な場面で活かせる |
・実務経験を積めないと正規の登録販売者と認められない ・立ち仕事が多く、体力が必要 ・商品の販売ノルマが課せられることもある |
登録販売者の資格は需要が高く、資格を取得すると医薬品の幅広い知識を得られるほか、就職や転職がしやすくなり、自分自身のキャリアアップにもつながるというメリットがあります。
しかし実務経験を積むまでは正規の登録販売者として働けず、また立ち仕事が多い体力勝負の仕事であるというデメリットもあります。
登録販売者として働くことは大変な面もありますが、身に着けた知識を仕事だけではなくプライベートでも活かせることなどから、メリットの方が大きい資格であるといえるのではないでしょうか。
登録販売者の仕事ってぶっちゃけどう?
| 登録販売者の仕事ってぶっちゃけどう? |
| ・最初のうちは知識不足で薬の相談に乗れないことがある
・一般的な接客スキルが必要 ・登録販売者が底辺の仕事と言われるのはなぜ? ・登録販売者の資格を活用できるかはその人次第 |
ここでは、登録販売者は実際どのように働いているのか、解説していきます。
最初のうちは知識不足で薬の相談に乗れないことがある
登録販売者としての経験が浅いうちは、医薬品や商品に関する知識不足でお客様からの相談にうまく回答できないことがあるでしょう。
登録販売者試験に合格すると医薬品に関する幅広い知識を得られますが、新しい医薬品は次々に開発されており、日々新たな医薬品がドラッグストアの店頭に並びます。
お客様からの健康相談や医薬品・商品に関する質問に適切に応えられるよう、資格を取得した後も常に医薬品について情報収集を続けていく必要があります。
一般的な接客スキルが必要
登録販売者は、お客様からの質問や相談に対応し、それぞれの症状に合った医薬品を紹介・販売することが主な仕事です。
お客様と円滑にコミュニケーションを取る接客スキルが求められるため、接客が苦手な人は登録販売者に向かないとも言えるかもしれません。
働く中でより多くのお客様の相談に対応することが、登録販売者としてのスキルアップにつながります。
登録販売者が底辺の仕事と言われるのはなぜ?
ドラッグストアやコンビニエンスストアなどで勤務している登録販売者は、医薬品の販売以外にもレジ打ちや商品の品出し・発注などの業務も行っています。
それらの仕事は、資格がなくてもできるものも多いことから「底辺の仕事」と呼ばれることがあるようです。
また、登録販売者は薬剤師以下の仕事だというイメージが広まっていたり、ドラッグストアやコンビニエンスストアでの仕事が多職種より下に見られていたりすることも原因ではないかと考えられます。
しかし、高齢化社会により医薬品の需要が高まっており、登録販売者が必要とされる場は今後さらに広がっていくと予想されています。
就職や転職が大変な時代の中で、医薬品のスペシャリストとして需要が高まっている登録販売者は、今後「底辺の仕事」と言われなくなると考えられます。
登録販売者の資格を活用できるかはその人次第
登録販売者の資格を取得した後に、
・転職がうまくいかなかった
・仕事が大変だった
・医薬品にかかわる仕事が思うようにできなかった
など、自分が思っていたような働き方ができず、理想と現実のギャップで「登録販売者の資格は役に立たない」と思ってしまう人が多いようです。
登録販売者の資格を活かして働くためには、薬の販売だけでなくレジ打ちなど様々な仕事を行いつつ、お客様の相談に適切に対応するために、医薬品に関する勉強や商品の情報収集をし続ける必要があります。
登録販売者の資格を活用できるかどうかは、働くその人次第であるといえるでしょう。
登録販売者試験の内容は?受験から合格後までの流れ
| 登録販売者試験の内容は?受験から合格後までの流れ |
| ・受験資格は不要!だれでも挑戦できる
・登録販売者の試験内容と合格基準 ・試験の難易度と合格率とは? ・登録販売者の試験当日の流れと注意点 ・合格した後にやるべきことは |
登録販売者の資格を取得するためには、年1回各都道府県で実施される『登録販売者試験』に合格する必要があります。
都道府県ごとに試験日や申し込み期間が異なる点に注意が必要です。
受験資格は不要!だれでも挑戦できる
2015年の薬事法の改正により受験資格が撤廃され、誰でも受験できるようになりました。
どの都道府県で受験してもよく、日程が被らなければ複数の都道府県で受験することが可能です。
登録販売者の試験内容と合格基準

引用元:ユーキャン公式HP
登録販売者試験の試験内容は以下の通りです。
| 試験内容 |
| 1.医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問/40分) |
| 2.人体の働きと医薬品(20問/40分) |
| 3.主な医薬品とその作用(40問/80分) |
| 4.薬事関係法規・制度(20問/40分) |
| 5.医薬品の適正使用・安全対策(20問/40分) |
試験はマークシート方式で、計120問を240分で解答します。
試験に合格するには、下記の合格基準を両方満たさなければなりません。
・総出題数(120問)に対する正答率が70%以上であること
・試験項目ごとの出題数に対する正答率が35%または40%以上であること(都道府県によって異なる)
登録販売者試験に合格するためには、全ての試験項目で確実に点数が取れるよう、まんべんなく学習を進めることが重要です。
試験の難易度と合格率とは?
| 過去6年間の登録販売者試験の合格率 | |||
| 実施年度 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 ※全国平均 |
| 2024年 | 54,526 | 25,459 | 46.7% |
| 2023年 | 52,214 | 22,814 | 43.7% |
| 2022年 | 55,606 | 24,707 | 44.4% |
| 2021年 | 61,070 | 30,082 | 49.3% |
| 2020年 | 52,960 | 21,952 | 41.5% |
| 2019年 | 65,288 | 28,328 | 43.4% |
(引用元:厚生労働省「これまでの登録販売者試験実施状況等について」)
登録販売者試験は受験資格がなく誰でも受験でき、例年の合格率は全国平均で40~50%とされています。
登録販売者試験の難易度はどれくらいか、登録販売者と同様受験資格のない資格試験の合格率と比較してみましょう。
受験資格が必要ない国家資格である司法書士の合格率は平均で3~4%、同じく受験資格が必要ない公的資格である日商簿記検定2級の合格率は平均で15~30%です。
登録販売者試験は受験者2~3人に1人は合格していることから、同じ受験条件の他資格と比べると、登録販売者試験の難易度は低い方であるといえるでしょう。
登録販売者は「国家資格」と「公的資格」のどちらなのか?
全日本医療品登録販売者協会のHPには以下の記載があります。
薬剤師は、医薬品に関する万般の専門家(国家資格者)です。これに対して、登録販売者は、第2類及び第3類に属する一般用医薬品販売という限定された範囲での専門家であり、国家資格ではありません。
(引用元:全日本医療品登録販売者協会公式HP)
登録販売者は都道府県知事の行う試験に合格することで取得できる資格であり、医薬品販売の専門家ですが、国家資格ではありません。
登録販売者の試験当日の流れと注意点
登録販売者試験は、午前・午後2時間ずつ、計4時間かけて行われますが、5章ある試験項目の順番は都道府県によって異なります。
事前に各都道府県の試験案内を確認して、午前・午後にそれぞれどの項目の試験があるのかを確認しておきましょう。
また、当日忘れ物がないよう、前日までに持ち物の確認をしておくと安心です。
当日必ず持参するもの
・受験票
・筆記用具
・腕時計
・不織布マスク、アルコール消毒液など
筆記用具に関しては、マークシート形式の試験のため鉛筆を忘れず持参しましょう。
また新型コロナウイルス対策のため、近年は試験当日は原則不織布マスクを着用するよう、各都道府県の受験案内に記載されています。忘れずに持参しましょう。
また、試験当日には以下のものも持参しておくと便利です。
・昼食
・試験勉強に使っていたテキスト
・羽織るもの
昼食は、休憩時間に買いに出る必要がないよう、あらかじめ持参すると安心です。
さらに休憩時間やお昼休憩の間にさっと復習ができるよう、テキストを持参しておくとよいでしょう。
また、試験会場は座席により空調の効き方に差が出ることがるため、「寒くて試験に集中できなかった・・・」とならないためにも、1枚薄手の羽織りものを持参していくのがおすすめです。
合格した後にやるべきことは
登録販売者の試験に合格した後、登録販売者として働くためにやるべきことは以下の通りです。
・勤務先の所在地の都道府県で販売従事登録をする
・正規の登録販売者になるため、実務経験を積む
・合格してからも外部研修への参加など勉強をし続けること
試験に合格後、合格を証明する書類を受け取ったら、まず勤務先のある都道府県で販売従事登録を行う必要があります。
販売従事登録とは、登録販売者として最初に働く事業所で一般医薬品の販売を行うために必要な手続きのことです。
販売従事登録には雇用証明書が必要なため、就職が決まっていない人は申請できない点に注意が必要です。
また、正規の登録販売者になるためには、前述の通り直近5年以内に2年以上の実務経験を積む必要がありますが、さらに厚生労働省の『登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン』に基づいて、年1回の外部研修の受講が義務付けられています。
独学?通信講座?資格取得におすすめの勉強法とは

引用元:資格のキャリカレ公式HP
| 独学?通信講座?資格取得におすすめの勉強法とは |
| ・独学でも資格を取ることは可能!
・独学が不安なら通信講座がおすすめ |
ここでは、登録販売者試験に合格するためにおすすめの勉強法について、解説していきます。
独学でも資格を取ることは可能!
登録販売者の資格は、独学でも取得できます。
大手通信講座ユーキャンによると、個人差はあるものの、独学で登録販売者試験に合格するために必要な勉強時間はおよそ400時間と言われています。
これは平日1日あたり3時間、休日1日当たり6時間勉強して約3か月かかる目安です。
独学で勉強する場合、自分の好きなペースで勉強できるのが大きなメリットといえますが、余裕を持って試験当日を迎えられるよう、早めに試験勉強を始めた方がよいでしょう。
また、自分で試験までのスケジュールを立ててしっかり勉強していく必要があり、仕事の合間に時間を見つけて自力で勉強をすすめるのが大変だというデメリットもあります。
さらに、独学の場合はテキストも自力で探す必要がありますが、法改正によって試験内容が変更になることもあるため、テキストを自力で選ぶ際は最新のテキストを使用して勉強するのが望ましいでしょう。
自分のペースで、お金をかけずに勉強したいという人は独学がおすすめです。
独学が不安なら通信講座がおすすめ
自力で学習を進めるのに不安がある場合には、通信講座がおすすめです。
通信講座を受講する場合、カリキュラムがあらかじめ用意されているため、自力で勉強計画を立てたりテキストを用意したりする必要がありません。
試験勉強でつまづいたとき、困ったときの相談に対応するサポートも充実しており、試験合格に必要な知識を短期間で身に着けられます。
通信講座は受講料がかかるというデメリットもあります。(平均30,000~40,000円程度)
しかし、自分で勉強のスケジュールやテキストを準備する必要がなく、わからないことがあったときにすぐに質問できる環境が整っていることは、試験勉強を進めるうえでとても大きなメリットです。
初めて登録販売者の資格試験に挑戦する場合は、ユーキャンの通信講座がおすすめです。
「ユーキャン 登録販売者資格取得講座」

引用元:ユーキャン公式HP
ユーキャンの通信講座は、現役の登録販売者からの支持が厚く、初めて勉強する人にもわかりやすいテキストでやさしく学べるのが特徴です。
医薬品の知識がなくても無理なく勉強できるカリキュラムで、合格まで手厚くサポートしてくれます。
また、標準受講期間は6か月と長めに設定されており、最長で14ヶ月まで添削指導や質問サービスなど全てのサービスを利用できるため、忙しくて勉強時間が取りづらい方も安心して受講できます。
短期間で効率的に試験対策を進めたいという人は、通信講座がおすすめです。
より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
試験に受かる気がしなくてやばい!合格のためのポイントは

引用元:資格のキャリカレ公式HP
| 合格のためのポイントは |
| ・自分の生活スタイルにあわせて勉強時間を確保する
・テキストや過去問を繰り返し勉強する ・覚えたことも徹底的に復習する |
資格取得に向けて勉強を始めたものの、試験に受かる気がしない…と不安に感じる方も多いと思います。
ここでは、登録販売者試験に合格するためのポイントを解説していきます。
自分の生活スタイルにあわせて勉強時間を確保する
登録販売者試験に合格するためには、最短でも3か月前後の勉強時間が必要と言われています。
登録販売者の求人サイトで、実際に登録販売者試験に合格した方々にアンケートを取ったところ、合格者の多くが約10か月~1年程度勉強期間を取っていましたが、実際には試験直前の3~4か月から最後の追い込み勉強をしていたようです。
勉強期間を長くとれば合格できるというわけではなく、勉強期間が長すぎると試験に対するモチベーションの維持が難しくなります。
自分のライフスタイルに合わせ、無理のないスケジュールを立てることが、合格への第一歩と言えるでしょう。
テキストや過去問を繰り返し勉強する
登録販売者試験の出題範囲は限られているため、試験の過去問を繰り返し解いて見直しをすることで確実に力が付きます。
登録販売者の試験勉強でテキストや過去問を繰り返し勉強するとよい理由は以下の通りです。
・試験の出題範囲がはっきりしているため
・過去問を解くことで試験の出題傾向を知れるため
登録販売者試験に合格するためには、1~5の項目それぞれで35~40%以上、全体で70%以上の正答率が必要であり、すべての項目をまんべんなく勉強していく必要があります。
各項目ごとに出題範囲がはっきりしているため、過去問を繰り返し解くことにより試験の出題傾向を把握できます。
また、過去に出題された問題が表現を変えて出題されることもあります。
登録販売者試験に合格するためには、どれだけ効率よく知識を覚えられるかが合格を左右します。
過去問を解くことで試験の出題傾向を知り、引っかかった部分をテキストを読み返し確認していきましょう。
覚えたことも徹底的に復習する
前述したとおり、登録販売者の試験に合格するためにはテキストや過去問を繰り返し勉強する必要があります。
ドイツの心理学者エビングハウスによると、人の脳は覚えたことを1日後には74%忘れ、1週間後には77%、さらに1か月後には79%忘れてしまうとされています。
この理論がさらに研究された結果、1回目の復習を「勉強した後24時間以内」、2回目を「1週間以内」、3回目を「1か月以内」に行うのが、記憶を定着させるのに効果的な復習のタイミングであることがわかっています。
つまり、一度勉強して覚えた内容は、時間をかけて定期的に繰り返し復習を重ねることで忘れにくくできるのです。
勉強を進める中で、一度覚えた内容や解けた過去問などはそのまま放置してしまいがちですが、テキストを読み返したり再度過去問を解き直したりするなど、定期的に復習するようにしましょう。
今後資格が廃止される?!登録販売者の将来性は?

引用元:資格のキャリカレ公式HP
まず、ドラッグストアなどで医薬品を販売するためには、登録販売者(または薬剤師)が店舗にいる必要があり、医薬品を販売する場合には、営業時間の中で半分以上の時間は登録販売者(または薬剤師)が常駐しなければいけないという「2分の1ルール」と呼ばれる決まりがありました。
しかし、24時間営業のコンビニエンスストアなど、長時間営業する店舗では12時間薬剤師や登録販売者を常駐させることは難しく、医薬品の販売に参入するのが困難な状況が続いており、2021年8月にこの「2分の1ルール」が撤廃されました。
この「2分の1ルール」の撤廃により、登録販売者や薬剤師を一定時間配置しなければならないという定めがなくなったため、登録販売者の配置が減ることで雇用が減少するのではないか?という懸念が生じたのです。
「登録販売者の雇用が減ってしまうということは、いずれは登録販売者の資格も廃止されるのでは・・・?」という心配の声もありますが、一方、規制緩和の影響で大手のフランチャイズチェーンなどが医薬品販売に参入しやすくなり、医薬品を取り扱う店舗や業種は増加傾向にあります。
さらに、医薬品を販売するにあたり、「登録販売者や薬剤師でなければ医薬品は売れない」という前提に変わりはありません。
先述の通り、「2分の1ルール」が廃止されたことにより、大手コンビニエンスストアは医薬品を扱う店舗を増やしており、さらに経済産業省の統計によると、登録販売者の主な就職先であるドラッグストアの店舗数は現在も増加し続けています。
登録販売者が必要な店舗や業種が増加している現状を考えると、登録販売者の将来性は高く、今後活躍の場はさらに広がっていくことが予想されます。
登録販売者に関するよくある質問
| 登録販売者に関するよくある質問 |
| 登録販売者の資格が廃止される可能性は? 登録販売者の資格を取っても就職できないことはある? 登録販売者試験の2023年の合格率は? 登録販売者試験に合格した後に働かないとどうなる? 登録販売者の離職率はどのくらい? 一度取得した資格がなくなることはあるの? 登録販売者は「食べていける」仕事? |
登録販売者に関するよくある質問をまとめました。
登録販売者の資格が廃止される可能性は?
A. 資格が廃止される可能性は低いと考えられます。
2021年8月に医薬品販売の規制が緩和され、コンビニエンスストアなどの他業種が医薬品を販売しやすくなった結果、医薬品を扱う店舗や業種は増加傾向にあります。
規制が緩和されても「登録販売者や薬剤師がいなければ医薬品は売れない」ことに変わりはないため、医薬品を販売する店舗や業種が増えれば、登録販売者の需要も増えていくと考えられます。
詳しくは『今後資格が廃止される?!登録販売者の将来性は』をご覧ください。
登録販売者の資格を取っても就職できないことはある?
A. 実務経験がない場合は就職が難しい可能性もあります。
登録販売者の資格を持ち、直近5年以内で2年以上の実務経験をすでに積んでいる場合、入社後即戦力として従事でき、一人で医薬品を販売することも可能です。
そのため、実務経験がない研修中の登録販売者と比べると、有利に就職活動を進められます。
しかし、資格取得後に実務経験を積んでいない登録販売者が就職活動をする場合は注意が必要です。
特に正社員の中途入社を目指す場合、企業側が即戦力を求めていることが多く、資格のみ取得して実務経験がない場合は採用されない場合もあります。
登録販売者の資格を取得した後に実務経験を積んでいない場合、未経験でも応募可能な求人を探すよう注意しましょう。
登録販売者試験の2024年の合格率は?
A. 2024年の合格率は、全国平均で46.7%です。
受験者数は54,526名、うち合格者は25,459名でした。
(参考:日本薬業研修センター「2024年度 登録販売者試験情報」 )
登録販売者試験に合格した後に働かないとどうなる?
A. 一度取得した資格が喪失することはありませんが、早めに働き始めるのがおすすめです。
登録販売者試験に一度合格すれば、その後働かなくても資格を喪失することはありません。
しかし、登録販売者は実務経験の条件を満たさなければ正規の登録販売者としては認められません。
登録販売者を採用する場合、企業側は未経験(またはブランクがある)登録販売者よりも、継続して実務経験を積んできた正規の登録販売者の方を優遇する傾向があります。
資格取得後に働いていない場合、医薬品に関する最新の環境や状況を把握できていないと判断され、いざ就職しようとした際に不利になってしまうのです。
登録販売者の離職率はどのくらい?
A. 登録販売者の主な就職先である小売業の離職率は比較的高いです。
登録販売者だけの離職率については根拠となる数字が発表されていませんが、登録販売者はドラッグストアなどの小売業で勤めることが多いです。
厚生労働省のデータによると、令和6年度の小売業の離職率(新卒入社の人が3年以内に離職した割合)は高卒48.6% で、大卒41.9%であり、比較的高いといえます。(参照元:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者))
一度取得した資格がなくなることはあるの?
A. 登録販売者の資格は、一度試験に合格すればなくなることはありません。
ただし、資格を持っているだけでは正規の登録販売者として認められず、直近5年以内に2年以上の実務経験を積む必要がある点に注意が必要です。
登録販売者は「食べていける」仕事?
A. 今後も需要が高まっていく可能性が高い、将来性のある仕事です。
登録販売者の主な就職先であるドラッグストアは全国各地にあり、現在も店舗数が増え続けています。
また2021年8月の規制緩和を受け、医薬品の販売に参入する企業は増加傾向にあり、大手コンビニ各社は医薬品を取り扱う店舗をさらに増やしていく方針を示しています。
登録販売者が活躍できる場所は今後も増え続けていくことが予想されており、登録販売者の需要も更に高まっていくことでしょう。
まとめ:ぶっちゃけ登録販売者の資格は役に立つのか?
登録販売者は、一般用医薬品を販売する企業にとって需要の高い資格です。
受験資格が必要なく、比較的取得しやすい資格であり、しかも一度試験に合格すれば資格がなくなることはありません。
登録販売者の資格を持っていれば全国各地に働ける場所があり、身に着けた知識を仕事だけでなくプライベートでも役立てられる点からも、登録販売者は役に立つ資格であるといえるでしょう。
少子高齢化が進む中、登録販売者の活躍の場はさらに広がっていくことが予想されます。
将来性が高く、今後も活躍が期待される登録販売者の資格取得に、この記事を参考にぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
登録販売者試験の勉強には通信講座という選択肢もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
登録販売者試験に関する関連記事
登録販売者試験については、以下の記事もご覧いただけます。