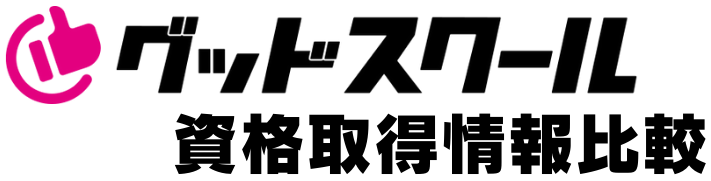建築士の中で最も難関とされる一級建築士試験について詳しくご存じでしょうか。
「合格率や必要な勉強時間など、実際どのくらいの難易度なのかは分からない」
「業務範囲や将来性・年収についてあまり分かっていない」など
一級建築士を目指す方にとって、難易度や勉強時間・将来的な年収などはとても気になる部分ですよね。
今回の記事では、一級建築士の難易度を中心に勉強時間や合格のポイント・将来性などについて紹介します。
一級建築士になりたい・受験を考えているという方はぜひご覧ください。
また、一級建築士の勉強は通信講座を利用した方法もおすすめです。
下記の記事にておすすめの通信講座を比較しておりますのでぜひご覧ください。
一級建築士は難易度が高い?合格率・合格基準点について
早速、一級建築士の難易度について、合格率・合格点の観点から見ていきましょう。
一級建築士試験は、学科試験と・製図試験に分かれており、それぞれの試験ごとに合格基準点というものが存在しています。
合格基準点を満たすことができなければ、たとえ他の部分で満点を取れていても足切り不合格になってしまうなど、形式においても難易度が高い試験です。
では、試験全体ではどのくらいの合格率・合格点となっているのか、学科試験・製図試験の合格率や合格点はどうなっているのか、下記で具体的に見ていきましょう。
一級建築士試験の難易度は高い!総合合格率・合格点
一級建築士試験全体の合格率をまとめましたのでご覧ください。
| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 総合合格率 | |
| 令和6年 | 28,067 | 3,010 | 8.8% |
| 令和5年 | 28,118 | 3,401 | 9.9% |
| 令和4年 | 30,007 | 3,473 | 9.9% |
| 令和3年 | 37,907 | 3,765 | 9.9% |
| 令和2年 | 35,783 | 3,796 | 10.6% |
| 令和元年 | 29,741 | 3,571 | 12.0% |
| 平成30年 | 30,545 | 3,827 | 12.5% |
| 平成29年 | 31,061 | 3,365 | 10.8% |
(引用元:総合資格学院公式HP)
受験者数は、令和元年以降から右肩上がりの傾向があり需要が高い試験だということが分かります。
また、合格率は平均して11.16%と、全体のおよそ9割の方が落ちてしまう試験で難易度が高いことも伺えます。
前述の通り、科目ごとだけでなく全体の合格基準点も存在しますので注意しましょう。
| 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
| 合格基準点 | 92/125 | 88/125 | 91/125 | 87/125 | 97/125 |
(引用元:資格の学校TAC公式HP)
総合的な合格基準点は毎年90点前後となっていますが、試験の難易度によって毎年若干の変動があります。
また、科目ごとの合格基準点の総和=総合合格基準点ではありませんので注意しましょう。
一級建築士学科試験の合格率・合格点
続いて、一級建築士学科試験の合格率・合格点について見ていきましょう。
学科試験は下記5つの科目に分けられており、前述のようにそれぞれの科目ごとに合格基準点が設けられています。
- 計画
- 環境・設備
- 法規
- 構造
- 施工
例えば、「計画」以外の科目で満点を取れていたとしても、「計画」の点数が合格基準点に満たない場合には足切り不合格となってしまいます。
つまり一級建築士学科試験は、何かに突出した知識ではなく、一級建築士に必要な知識を満遍なく備えていることが試される試験です。
それでは、年度ごとの合格率・合格点の推移を見ていきましょう。
| 実施年 | 計画 (基/出) |
環境設備 (基/出) |
法規 (基/出) |
構造 (基/出) |
施工 (基/出) |
総得点 (基/出) |
合格率 |
| 令和6年 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 92/125 | 23.3% |
| 令和5年 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 88/125 | 16.2% |
| 令和4年 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 91/125 | 21.0% |
| 令和3年 | 10/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 87/125 | 15.2% |
| 令和2年 | 11/20 | 10/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 97/125 | 22.8% |
(引用:資格の学校TAC公式HP)
科目ごとおおよその基準点が毎年定められており、大きな変動はありません。
しかし、科目ごとの難易度や試験全体の調整として、若干の変動が見られますのであくまで目安として認識しておきましょう。
学科試験の合格率は平均して19.4%なため、学科試験において全体のおよそ8割の受験者が落ちていることが分かります。
一級建築士設計製図試験の合格率・合格点
続いて、一級建築士の設計製図試験の合格率・合格点について見ていきましょう。
製図試験はランクによって合格不合格が決まるため、合格点はありません。
| ランク | 内容 |
| I | 「知識及び技能」を有するもの |
| II | 「知識及び技能」が不足しているもの |
| III | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |
| IV | 設計条件及び要求図書に対する重大な不適合に該当するもの |
採点側の基準によってランク付け(評価)が行われ、ランクI〜IVの中でランクIのみが合格です。
こちらを踏まえた上で、受験者数や合格率について見ていきましょう。
| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 | |
| 令和6年 | 11,306 | 3,010 | 26.6% |
| 令和5年 | 10,238 | 3,401 | 33.2% |
| 令和4年 | 10,509 | 3,473 | 33.0% |
| 令和3年 | 10,499 | 3,765 | 35.9% |
| 令和2年 | 11,035 | 3,796 | 34.4% |
| 令和元年 | 10月13日実施 4,214 12月8日実施 5,937 |
10月13日実施 4,214 12月8日実施 5,937 |
10月13日実施 36.6% 12月8日実施 34.2% |
| 平成30年 | 9,251 | 3,827 | 41.4% |
| 平成29年 | 8,931 | 3,365 | 37.7% |
合格率は35%以上となっており、学科試験に比べると合格率は高い試験となっています。
しかし、学科試験とは異なる知識・能力が問われる試験ですので、十分な対策が必要となるでしょう。
また学科試験同様、製図試験にも足切りの基準が設けられており、国土交通省によって下記のように設定されています。
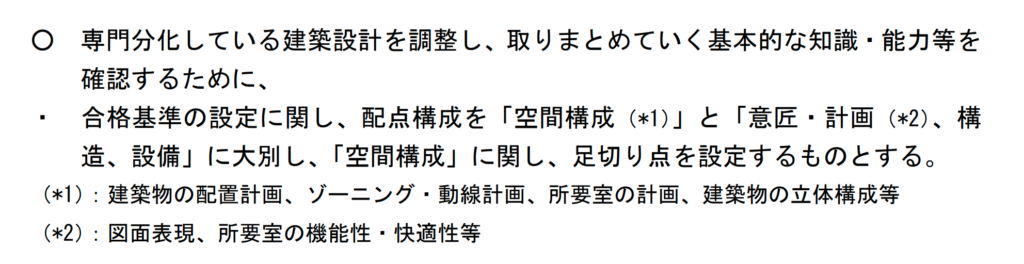
(引用元:国土交通省公式HP)
「空間構成」の範囲に関して足切り点が設定されているため、製図試験の中でも、特に「空間構成」の部分に関してミスをしてしまうと、採点の土俵にも上がれない可能性がありますので注意しましょう。
一級建築士試験合格に必要な勉強時間
一級建築士試験は難易度が高いことに加え、学科試験と製図試験があり、勉強する範囲もとても広いです。
一般的に一級建築士試験は、合格に700〜1,500時間くらいの勉強時間が必要だといわれています。
1級建築士の試験に合格するための勉強時間の目安は、700〜1,500時間といわれています。
(引用元:LIFULL公式HP)
仮に1日2時間の勉強時間を確保できたとしても、およそ1年はかかるほどの勉強時間が必要です。
一級建築士試験に合格した方は、1日どのくらいの勉強時間で、どんなスケジュールを立てて試験まで勉強していたのでしょうか。
下記で詳しく見ていきましょう。
一級建築士試験|1日の勉強時間
前述の通り一級建築士試験の合格には、経験の有無にもよりますが700〜1,500時間が必要です。
自身の学習状況や経験・何年後の試験に合格したいのかを考え決定していきましょう。
たとえば、全く経験の無い初学者が1年後の合格を目指す場合には、1日約3時間の勉強が必要です。
(必要勉強時間:1,000時間・日数:365日で算出)
また、「1日1〜2時間しか時間が取れないから2年後の試験を受験しよう」など、確保できる時間から受験時期を考えることもできます。
状況を正確に把握し、自分はどのくらいの期間・ペースで勉強を進めていく必要があるのか算出してみましょう。
一級建築士試験までの勉強スケジュール
一級建築士試験には700〜1,500時間の勉強時間が必要だといわれていますが、初学者の場合は最低でも1,000時間の勉強時間が必要となるでしょう。
勉強時間の目安は、初学者の場合1000~1500時間といわれています。
(引用元:スタディング公式HP)
この1,000時間を実際に1年間でこなし合格した方は、下記のようなスケジュールを立てて勉強していたそうです。
1000時間÷52週=19.2時間になりますので、週に19時間程度の勉強が必要であるという事になります。
〜中略〜
建築設計事務所に勤めていた筆者の場合
【平日】 2.5時間×5日=12.5時間 【土日】 3.25時間×2日=6.5時間
(引用元:資格取得エクスプレスbyスタディング)
この方の場合には、休日よりも平日に力を入れて勉強を進めていたようですが、状況によっては下記のように休日に力を入れて進めたいという方もいるでしょう。
週19時間を想定
【平日】1時間×5日=5時間 【休日】7時間×2日=14時間
このように、必要な勉強のスケジュールは人それぞれ異なり、確保できる勉強時間・経験の有無によっても変動します。
しかし、どのような場合でもしっかりと計画を立てることがとても重要です。
1年後の試験をターゲットとした場合に、1日何時間勉強するのか、学科・製図試験に向けてどのような勉強をするのかを試験日から逆算して、スケジュールを立てていきましょう。
会社員の方などは、平日と休日で確保できる勉強時間が大きく異なると思いますので、試験日までの大枠のスケジュールを立てた後は、一週間ごとの勉強スケジュールを立てると良いでしょう。
最短どのくらいの勉強時間で合格できる?
繰り返しますが、一級建築士の合格に必要な勉強時間は人それぞれ異なります。
ネット上では、500時間ほどの勉強時間で合格できるという方もいますが、もっと時間がかかる方も珍しくありません。
経験者の場合、500時間ほどの学習で合格する方もいます。
(引用元:スタディング公式HP)
たとえば、「DADDY SOUL」運営者の「パパ魂」さんは、会社員として働きながら一級建築士試験を受験した際、2回目で学科試験を突破されていますが、学科試験のみで2,000時間以上勉強したと発信されています。
因みに僕の学科勉強時間は、1年目1224時間、2年目1119時間、学科突破するまでトータルで2343時間かかりました。。。
(引用元:DADDY SOUL)
人それぞれ合格にかかる時間は違いますが、前述のように一級建築士試験は初学者の場合、最低でも1,000時間必要といわれている試験ですので、最短でも1,000時間必要だと理解しておくと良いでしょう。
一級建築士の偏差値はどのくらい?他の国家資格と難易度を比較
合格率や勉強時間を紹介したことで、一級建築士の難易度について理解が深まったのではないでしょうか。
続いて、さらに一級建築士の難易度についての理解を深めるため、一級建築士の大学別合格実績や他の国家資格との比較を紹介します。
一級建築士試験の偏差値は明確に定義することは難しいため、合格実績のある大学の学部偏差値などから推察していきます。
それでは、大学別の合格実績や他の国家資格との比較を見ていきましょう。
一級建築士の偏差値|難易度を大学別の合格実績で比較
早速ですが、一級建築士試験の大学別の合格実績をご覧ください。
| 学校名 | 建築学科偏差値 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 日本大学 | 57 | 153名 |
| 東京理科大学 | 62〜66 | 128名 |
| 芝浦工業大学 | 61 | 96名 |
| 近畿大学 | 50 | 87名 |
| 早稲田大学 | 66 | 79名 |
| 明治大学 | 61 | 70名 |
| 千葉大学 | 63 | 68名 |
| 工学院大学 | 59 | 63名 |
| 京都工芸繊維大学 | 58〜64 | 57名 |
| 京都大学 | 69 | 56名 |
| 神戸大学 | 63 | 54名 |
| 東京都市大学(武蔵工業大学) | 59 | 51名 |
| 法政大学 | 60 | 51名 |
| など | ||
(参照元:公益財産法人建築技術普及センター公式HP・東進ハイスクール公式HP・マナビジョン)
日本大学が一番多く、続いて東京理科大学、芝浦工業大学などが続く形となっていました。
このように見てみると、一級建築士試験は、偏差値60前後の人が受けており、多くの人が合格している試験だということが分かります。
また、工業大学などの建築系の学部が強い大学群も名を連ねています。
そのような中で日本大学が一番合格者数が多い理由としては、そもそもの受験者が多いことも関係しているでしょう。
国家資格と難易度を比較!一級建築士が難しいといわれる理由
続いて、他の国家資格との比較を見ていきましょう。
| 資格名 | 受験者数 | 合格率 |
| 公認会計士 | 14,192名 | 9.6% |
| 弁護士 | 3,082名 | 45.52% |
| 医師 | 9,222名 | 91.7% |
| 税理士 | 27,299名 | 18.8% |
| 一級建築士 | 37,907名 | 9.9% |
| 一級建築施工管理技士 | 12,813名 | 52.4% |
| 建築設備士 | 2,813名 | 31.4% |
このように一級建築士試験は、受験者数が最も多いにもかかわらず、合格率が公認会計士と同等となっているなど、試験に落ちてしまう方が非常に多い、難しい試験だということが分かるでしょう。
また一級建築士は、同じ建築関連の資格である施工管理技士や建築整備士より、合格率が圧倒的に低い点からも難易度の高さが窺えます。
もちろんそれぞれの試験には特性があるため、一概に難易度を判断することは難しいですが、受験者数・合格率は難易度を測る指標となるでしょう。
一級建築士の平均年収は?取得後の将来性
続いて、一級建築士の平均年収や資格取得後の将来性などについて紹介します。
一級建築士の平均年収はおよそ700万円前後となっており、年齢や経験によって収入が大きく異なります。
(参照元:厚生労働省|賃金構造基本統計調査)
令和2年度の給与所得者の平均年収が433万円であるため、一級建築士になることができれば平均よりも多い給与を期待することができるでしょう。
一級建築士には建築業務における制限がないため、年齢と共に経験を積んでいくことでさまざまなことができるようになっていくため、比例して年収も上がってく傾向があります。
それでは、具体的に平均年収の推移や活かせる仕事・将来性について見ていきましょう。
一級建築士の平均年収
前述の通り、一級建築士の平均年収はおよそ700万円前後ですが、年齢・経験によって年収には大きな差が存在しています。
| 年齢 | 年収額 |
|---|---|
| 25~29歳 | 559万9,200円 |
| 30~34歳 | 797万5,700円 |
| 35~39歳 | 755万3,200円 |
| 40~44歳 | 826万7,200円 |
| 45~49歳 | 782万3,200円 |
| 50~54歳 | 742万9,200円 |
| 55~59歳 | 801万9,700円 |
| 60~64歳 | 632万4,800円 |
(引用元:読売理工医療福祉専門学校公式HP)
一般的には、年齢と共に経験を積み重ね年収が上がっていく傾向にあり、40~44歳のピーク時の年収は800万円を超えます。
その後は緩やかに減少傾向となるため、20代などの早いうちに資格を取得することが望ましいでしょう。
また、この年収はあくまで平均値となるため、独立・開業をしている一級建築士の中には年収1,000万円を超えているという人もいます。
一級建築士は経験の積み方や資格の活かし方によって、年収1,000万円を超えることも可能な資格です。
一級建築士が活かせる仕事
少子高齢化や働き方の変化によって、これから建築の仕事がずっと続いていくのか不安を持たれている方もいらっしゃると思います。
しかし、一級建築士ともなれば資格・知識を活かせる仕事がとても多く、一級建築士から転職するという方も珍しくありません。
具体的には下記のような仕事に、一級建築士の資格を活かすことが可能です。
| 職種 | 内容 |
| 公務員 | 公共建築物の施工・建築確認申請などの受付業務など |
| 施工管理 | 一級建築士資格保有者を施工管理業務で募集している場合など |
| 大手企業の店舗展開 | 大手企業の新規出店する店舗のデザインや施工監理など |
| 街づくりなどのコンサルタント | 建物の設計だけでなく、地域調査や街づくりとの連携などを行う |
| 不動産関連 | 不動産企業における住宅診断(ホームインスペクション)など |
(参考元:株式会社Mirai style公式HP)
ご紹介したように、一級建築士は建物の設計以外の業務にも知識や経験を活かすことが可能なことに加え、国家試験であること、難易度の高さから資格自体が強いため、さまざまな場面で重宝されるでしょう。
反対に、「街づくりに関わる」など最終的な大きい目標に向けて一級建築士の取得を検討してもいいかもしれません。
一級建築士を取得するメリット
平均年収も高く、建築士以外でも活かせる幅が広いなど既にメリットが多い資格ですが、他にはどんなメリットがあるのでしょうか。
一級建築士を取得するメリットは下記の3点です。
- 大規模な建物まで設計可能
- 他の資格の受験要件や免除要件に利用可能
- 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士を目指せる
一番のメリットとしては、国内に立つどんな大きさの建物でも設計することが可能な点でしょう。
一級建築士として、二級建築士ではできなかった大きさの建物を設計したり、より大きなプロジェクトに建築士として関われたりと、制限がなくなることで行える業務の幅が大きく広がります。
また、一級建築士を持っていることで、他の資格の受験要件や免除要件として利用することが可能です。
中には国家試験も含まれ、弁理士の論文式試験や土地家屋調査士の筆記試験が免除されます。
そして、一級建築士には、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士というさらに上の資格が存在します。
それぞれの受験資格として、一級建築士として5年以上の実務経験が必要となるため、一級建築士試験に合格することが更にステップアップするためのスタート地点となるのです。
一級建築士の勉強法・合格のポイント
続いて、一級建築士の勉強法・合格のポイントについて紹介します。
一級建築士試験は、これまでご紹介したとおり難易度がとても高く必要な勉強時間も多いです。
一級建築士合格のためにも、下記4つのポイントを押さえて勉強を進めていきましょう。
- 試験日までの計画を立てる
- 問題集・過去問をひたすら解く
- スキマ時間も動画で学習
- 通信講座を活用する
4つのポイントは、現場・技術者系の資格講座のみに特化しているSAT、試験合格に必要な「最小限の学習を極める」ことが特徴のスタディングの情報を参考にしました。
試験日までの計画を立てる
まずは、試験日までの計画を立てましょう。
後述しますが、一級建築士試験は毎年7月の第4日曜日に実施されることが多いです。
オリンピックの年は混雑を避けるため2週間早めての実施となりましたが、余程のイレギュラーがない限り変更はありませんので、7月の後半と考えて計画を立てましょう。
現在の自分は合格までに何時間勉強が必要そうなのか、学科・製図試験の勉強はどのように進めるべきかなどを元に、全体の計画・月毎の計画など、期間ごとの計画を立てていきます。
また計画を立てる際には、必ず定量的な数値に落とし込むところまで行いましょう。
例:×法規について勉強する ◯法規について50時間勉強する・テキストを2週するなど
そうすることで、現在の自分の進度を振り返りやすく、計画を再構築する際にも役立ちます。
一度立てた計画を忠実に守り続ける必要はなく、勉強を進めていく中で計画も改善をしながら試験まで進んでいきましょう。
問題集・過去問をひたすら解く
一級建築士試験は、問題集・過去問をひたすら解くところから始めましょう。
特に、基礎知識がある程度身についている状態であれば、過去問での学習が非常に重要です。
市販のテキストは、インプットする際にはとても役立ちますが知識のアウトプットには不向きなため、分かったつもりになってしまう可能性が非常に高いでしょう。
そこで、過去問を解いて自分の得意・苦手分野を把握することが大切になってきます。
参考書は知識のインプットはできてもアウトプットができない〜中略〜過去問を一緒に解き進めながら、自分が得意とする分野、苦手とする分野を把握し、試験の全体像や自分の現状を理解しましょう。
(引用元:SAT公式HP)
一級建築士の学科試験は、合格基準点があり満遍な知識が求められますので、得意なところを伸ばすよりも苦手分野を無くすことを優先しましょう。
過去問にて苦手分野を特定→テキストでインプット→問題集・過去問でひたすらアウトプットという流れがおすすめです。
スキマ時間も動画・アプリで学習
一級建築士を目指す方は、大手のゼネコンや設計事務所に勤務している方などが多く、本業の傍ら勉強を行う方がほとんどでしょう。
ただでさえ割ける時間が少ないため、通勤時間や移動時間などのちょっとしたスキマ時間が試験合格にはとても重要です。
隙間時間に1問でも多くの問題を理解しておくことで合格する力が身に付きます。 〜中略〜 アプリであれば、通勤途中や仕事の隙間時間でも場所をとりません。
(引用元:SAT公式HP)
スマホ1つあれば、大きなテキストを持ち歩く必要もないため、一級建築士試験に関する動画コンテンツやアプリをダウンロードしておき、いつでも勉強できるようにしておくと良いでしょう。
通信講座を活用する
一級建築士は独学で合格することも十分に可能な資格ですが、通信講座を活用することでより効率的に学習を進めることができます。
特に、設計製図試験の勉強は独学よりも誰かに学ぶことが、合格への近道です。
なぜなら独学の場合、製図用の参考資料が少ないことに加え、第三者からの添削を受けることができないからです。
通信講座では製図の想定問題なども用意されているため、より実践的に学びを進めることができます。
一級建築士の通信講座はさまざまな企業が提供していますが、中でも資格の学校TACがおすすめです。
TACでは、一級建築士口座が合計で9つも用意されており、初学者の方が包括的に学ぶことから自分の学習したい項目のみを受講するといったことも選択できます。
一級建築士試験の概要・内容
続いて、一級建築士試験の概要・内容について紹介します。
- 試験日程・会場
毎年7月の第4日曜日に学科試験が実施され、受検者の希望エリアに基づき公開会場で受検可能。 - 申し込み方法
基本的にはWEB申し込みのみ。 - 受験資格(下記どちらか)
大学の建築学科などで指定科目を修めて卒業すること
二級建築士免許を取得していること
一級建築士試験全体の概要は上記のようになっております。
平成30年の12月から受験資格が緩和されており、一級建築士の受験には実務経験が問われなくなりました。
しかし、合格後の免許登録には実務経験が必要などの要件が別途必要ですので注意しましょう。
それでは、学科試験・設計製図試験の概要・内容について見ていきましょう。
一級建築士|学科試験の概要・内容
一級建築士学科試験の概要は下記の通りです。
- 試験日程
7月の第4日曜日 - 試験時間
学科I・II(計画・環境設備):2時間
学科III(法規):1時間45分
学科VI・V(構造・施工):2時間45分 - 合格発表
9月初旬
学科試験は3つに分けて行われ、休憩時間などを含めると丸一日かかる試験です。
合格発表は毎年9月の初旬頃に行われることが多く、合格をした方のみが製図試験に進むことができます。
学科試験の内容は下記の通りです。
| 科目 | 問題数 | 内容 |
| 建築計画 | 20問 | 「計画各論」「建築史」「都市計画」「環境工学」「建築設備」の5分野からなる科目 |
| 建築環境・設備 | 20問 | 「環境工学」と「建築設備」の2分野からなる科目 |
| 建築法規 | 30問 | 「建築基準法」が中心 「建築士法」「バリアフリー法」などからも出題される科目 |
| 建築構造 | 30問 | 「力学」「各種構造」「材料」の3分野からなる科目 |
| 建築施工 | 25問 | 建築工事の準備から完成までの内容が出題される科目 |
建築法規は、試験時間も1科目で1時間45分と多く、問題数も30問となっており、試験全体における比重が大きい科目です。
全体の問題数は、125問となっており1問1点の点数が与えられます。合格の基準としては、毎年全体の7割強を正答する水準に定められています。
一級建築士|設計製図試験の概要・内容
続いて、設計製図試験の概要・内容について見ていきましょう。
- 試験日程
10月の第2日曜日 - 設計製図の課題発表
7月下旬ごろ - 試験時間
設計製図:6時間30分 - 合格発表
12月下旬
合格発表は試験の2・3ヶ月後となっており、製図試験の合格=一級建築士試験合格です。
試験時間が6時間30分ととても長く感じられますが、実際の試験では製図が未完成となってしまう方もいるほど、タイトな時間設定となっています。
製図試験の課題は毎年7月の下旬頃に発表されるため、学科試験終了後の3ヶ月ほどで課題に合わせた対策を勉強の仕上げとして行っていきます。
過去の製図試験の課題についてまとめましたのでご覧ください。
| 年度 | 課題 |
| 令和6年 | 大学 |
| 令和5年 | 図書館 |
| 令和4年 | 事務所ビル |
| 令和3年 | 集合住宅 |
| 令和2年 | 高齢者介護施設 |
| 令和元年 | 美術館の分館 |
| 平成30年 | 健康づくりのためのスポーツ施設 |
| 平成29年 | 小規模なリゾートホテル |
| 平成28年 | 子ども・子育て支援センター |
| 平成27年 | 市街地に建つデイサービス付高齢者向け集合住宅 |
| 平成26年 | 温浴施設のある「道の駅」 |
| 平成25年 | 大学のセミナーハウス |
一級建築士と二級建築士の違い
続いて、一級建築士と二級建築士の違いについて見ていきましょう。
一級建築士と二級建築士の最大の違いは、設計できる建物に制限があるかどうかという点です。
その他、細かい点で見ると免許の交付元が違うなど与えられている権利が大きく異なります。
このような違いは、試験の難易度から仕事内容・年収にも違いを生んでいますので、下記3つの観点から詳しく見ていきましょう。
- 難易度・合格率や合格点の違い
- 平均年収の違い
- 将来性・仕事内容の違い
まずは、難易度合格率・合格点の違いからです。
難易度・合格率や合格点の違い
一級建築士・二級建築士では一級建築士の方が難易度が高いですが、どのくらい合格率や合格点が違うのでしょうか。
下記の表にまとめましたのでご覧ください。(2024年度)
| 受験者数 | 合格点(学科) | 合格率 | |
| 一級建築士試験 | 28,067 | 92/125 | 8.8% |
| 二級建築士試験 | 17,602 | 60/100 | 21.8% |
2024年度にて比較を行ってみましたが、合格率に10%以上も差があることが分かりました。
なぜここまで合格率に乖離があるのかというと、問題が難しいというのはもちろんのこと、合格基準点の水準が上がっていることが関係していると思われます。
二級建築士では6割で良かった基準が、一級では7割強も必要となるため合格者が大きく下がっているのでしょう。
平均年収の違い
一級建築士と二級建築士にはどの程度平均年収の違いがあるのでしょうか。
| 資格 | 平均年収 |
| 一級建築士 | 700万円前後 |
| 二級建築士 | 500万円前後 |
2級建築士の平均年収はおよそ500万円前後
(引用元:SAT公式HP)
一級建築士の年収は、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」で公表されています。 2019年の調査結果によると、平均年収はおよそ700万円です。
(引用元:読売理工医療福祉専門学校公式HP)
今回ご紹介したのは平均年収ですが、一級建築士と二級建築士の間にはおよそ200万円ほどの乖離があるようです。
200万となると月に16万円ほども違いますので、大きな差となるでしょう。
しかし、あくまで平均年収ですので二級建築士だから稼げないという訳ではありません。
二級建築士の方の中にも、自分だけのポジションを確立し平均年収を大きく上回る金額を稼いでいる方もいらっしゃいます。
将来性・仕事内容の違い
一級建築士と二級建築士では、将来性や仕事内容にどのような違いがあるのでしょうか。
両者の大きな違いは、設計できる建造物の大きさに制限がある点です。
一軒家の住宅などであれば、二級建築士でも設計可能ですが、一級建築士であれば制限がないため、日本国内に立つすべての建物を設計できます。
建築士のキャリアは年数が経つごとに経験やノウハウが蓄積されていくため、どんどんと重宝される人材になっていくでしょう。
しかし、一級建築士と二級建築士では扱える建造物の大きさに違いがあるため、プロジェクトの大きさも異なってきます。
例えば、一級建築士であれば、首都圏のシンボルとなるような建造物に関わる機会があるかもしれませんが、二級建築士では難しいでしょう。
一概に一級建築士の方が良いという訳ではなく、仕事の大きさ・内容に違いが出てくる点は知っておく必要があります。
一級建築士についてよくある質問
| 一級建築士についてよくある質問 |
|
最後に一級建築士試験についてよくある質問をまとめましたのでご覧ください。
一級建築士は独学では無理?
一級建築士試験は独学で合格することも可能です。
実際に、「Kuroの勉強法」を運営しているKuroさんは、学科・製図試験共に独学で一発合格していますし、「一級建築士独学ブログ」を運営しているいっきゅうさんは、2年で合格しています。
しかし、独学での合格者は母数としては少なく、合格者の約9割は何らかの形で講座を利用しているため、独学の場合には相当な覚悟で勉強する必要があるでしょう。
建築士資格を取得するにあたっては、〜中略〜53.2%の人が通学型資格講座を利用・35.1%の人がオンライン資格講座を利用したことがわかりました。
(引用元:資格取得エクスプレスbyスタディング)
また製図試験では、独学の場合、何が正しく何が間違っているのか判断が難しいため、経験者などに指導してもらう方が有利であることは間違い無いでしょう。
独学での合格は、自分で立てたスケジュールをやり抜くことができ、周りにサポートしてくれる人(経験者)がいるという状況でないとかなり難しいです。
合格者の中には、完全に独学という訳ではなく、適宜講座を利用している方もいますので、苦手な分野のみ講座を受講するという選択肢もあります。
資格の学校TACでは、一級建築士に関わる講座を9つも提供しており、製図試験に特化した講座もありますのでとてもおすすめです。
一級建築士に受験資格はある?
一級建築士の受験資格は下記のうちどれかに当てはまっていることが条件です。
大学、短期大学、高等専門学校において
・ 入学年が2009年度(平成21年度)以降:指定科目を修めて卒業した者
・ 入学年が2008年度(平成20年度)以前:建築または土木の課程を修めて卒業した者
2級建築士の資格保有者
国土交通大臣が、上記の二者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
建築設備士の資格保有者
平成30年度の変更により、一級建築士試験の受験に限っては実務経験を必要としなくなりました。
国土交通大臣に認めてもらうことは現実的ではないため、学校において指定の科目を修めるか、2級建築士・建築整備士の資格を有することが一級建築士の受験には必要になるでしょう。
一級建築士の登録要件とは
一級建築士は試験に合格すればすぐになれるものではなく、登録要件を満たした上で一級建築士として登録されることが必要です。
一級建築士の登録には実務経験が問われ、上記で紹介した受験資格のどれに該当するかによって必要な経験年数が異なります。
| 一級建築士の受験要件 | 登録に必要な実務経験 |
| 大学 | 2年以上 |
| 短期大学(3年) | 3年以上 |
| 短期大学(2年)・高等専門学校 | 4年以上 |
| 二級建築士 | 2級建築士として4年以上 |
| 建築設備士 | 建築設備士として4年以上 |
| 国土交通大臣が同等と認めるもの | 所定の年数以上 |
(引用元:スタディング公式HP)
新しい制度に変わったことによって、試験に合格をしてから実務経験を積むという選択肢も取れるようになりました。
以前は、実務経験を積んでからしか試験を受験できませんでしたが、現在では実務経験を積みながら試験に挑戦し、合格することができれば、実務経験を満たしたタイミングで一級建築士として登録することが可能です。
一級建築士の合格には何年かかる?
前提として一級建築士の合格は、人によってかかる年数が異なるため、何年かかると明言することできません。
ただ、一級建築士試験は1回で合格できないことも決して珍しくはない、非常に難易度が高い試験です。
一級建築士は「数年かけて取得する」資格
一級建築士の資格取得で大事なのは「試験結果が不合格だったとしても、1回で諦めないこと」
(引用元:施工管理求人.com)
仮に1回目で落ちてしまっても諦めず、自分の中で最短で合格できるように計画を立てて勉強を進めていくと良いでしょう。
一級建築士はどんな人に向いている?
最後に一級建築士に向いている人の特徴を紹介します。
- ものづくり・建築が好き
- 好奇心旺盛
- 責任感がある
- コミュニケーション能力が高い
- 大きな建造物が作りたい など
他にもたくさんの特徴がありますが、上記の5点を挙げました。
建築士に「向いている人・活躍する人」の条件とは?
・モノ作りが好き
・建築物が好き、間取りを考えるのが好き
・創造するのが好き、考えるのが好き求められる能力
・実はコミュニケーション能力が大事!・責任感が大事!
(引用元:新潟工科専門学校)
1〜4は一級建築士というよりも、建築士自体に向いている人の特徴をまとめました。
建築士は、建造物を作るため物作りや建築を好きであることや建築に対する好奇心などがとても大切にです。
また、全体の設計行うため現場全体に対する責任も大きく、さまざまな方と話す必要があるためコミュニケーション能力が求められます。
二級建築士と異なり、一級建築士には建造物の制限がないため、大きな建造物が作りたいなどの大きな目標を持っている方には向いている資格だといえるでしょう。
まとめ
ここまで一級建築士について難易度を中心として、将来性や年収・二級建築士との違いなど、さまざまな観点から解説しました。
一級建築士試験は、国家試験の中でも難易度が高いグループに属する試験で、必要な勉強時間も1,000時間といわれているなどとても難しい試験です。
合格率は毎年10%ほどとなっており、およそ9割の方が落ちてしまう試験ですが、独学での合格も不可能ではありません。
しかし、勉強する科目も多く実技として製図試験もあるため、通信講座などを利用して第三者からの指導を受けながら勉強するとより効率的に学習を進めることができるでしょう。
資格自体の将来性も高く、実務経験を積んでいくことで経験・ノウハウが蓄積され年収のUP・業務範囲の拡大を望むことが可能です。
建造物の設計に限らず、建築士以外でも資格を活かすことができるため、建築や不動産に関わる方の選択肢を大きく広げることができる資格でしょう。
この記事を参考に一級建築士の受験を検討してみてはいかがでしょうか。
また下記の記事にて、一級建築士のおすすめの通信講座を比較しておりますのでぜひご覧ください。